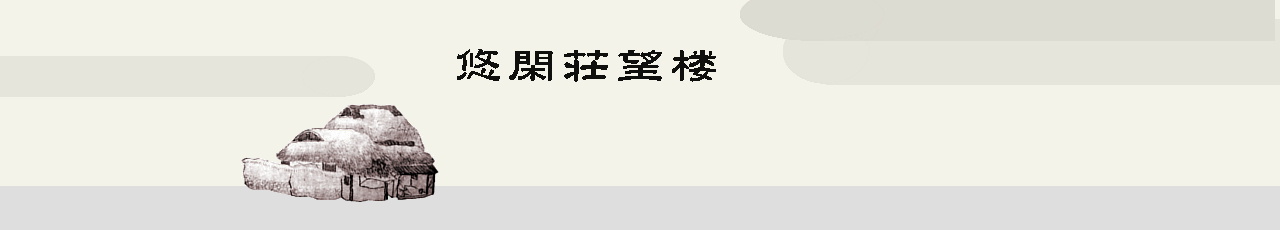「(略)学校なんて無理に行くことないんだ。行きたくなけりゃ行かなきゃいい。僕もよく知ってる。あれはひどいところだよ。嫌なやつがでかい顔してる。下らない教師が威張ってる。はっきり言って教師の八〇パーセントまでは無能力者かサディストだ。あるいは無能力者でサディストだ。ストレスが溜まっていて、それを嫌らしいやり方で生徒にぶっつける。意味のない細かい規則が多すぎる。人の個性を押し潰すようなシステムができあがっていて、想像力のかけらもない馬鹿な奴がよい成績をとってる。昔だってそうだった。今でもきっとそうだろう。そういうことって変わらないんだ」
「本当にそう思う?」
「もちろん。学校のくだらなさについてなら一時間だってしゃべれる」
ダンス・ダンス・ダンス 上巻P325頁 村上春樹
主人公「僕」と旅の途中で出会った美少女ユキとの会話。中学校に行かないユキに「僕」が語りかける。日本で最も高い人気を誇る小説家の作品中の会話である。この本だけで日本で二百万部位上売れているらしい。もちろん作品中主人公の言葉で、村上本人の言葉ではない。しかし「風の歌・・」から本作品までの「僕」の目線は作者に近い。学校教育の駄目さ加減については彼の小説に繰り返し出てくる。逆に学校に肯定的な意味を与えるような記述を少なくとも私は思い浮かべることが出来ない。彼の読者はこの言葉を共感をもって読むはずだ。がんばって教師やっていた職歴数年の私もある種の爽快感をもってこの会話を読んだと記憶しているし、その印象は今でもあまり変わりらない。
学校って基本的にこんな所、でも日本の子供達ほぼ全員が学校に通っていて、少しはましな場所にするために何かやることはあるはずだ。そう考えながら仕事をしてきた。村上春樹の書物を、私が拘ってきた日本の伝統的共同体意識から離脱した主人公の、社会に対する違和感の表明と新しい生き方模索として読んできた。彼の新刊をいつも楽しみにしている。