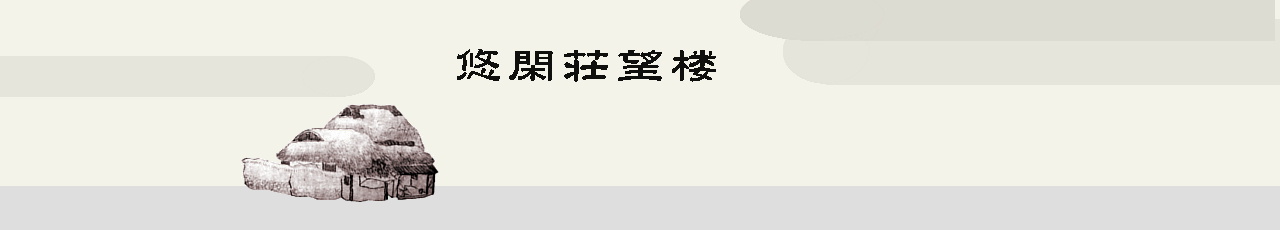最近他人の気持ちがうまく理解できない生徒が増えているように思えてならない。というか、他者を了解する能力と表現した方がいいかもしれない。三十年位以前の生徒を今思い出すと、その当時はあまり意識しなかった特徴を上げることができる。同時に今の生徒が失ったものが見えてくる。
二十代で教員を始めた頃、こちらも若く血気盛んで一方教員のトレーニングは足りないから生徒と随分トラブルを引き起こした。これが教員の辛い成長の過程なのだけど。その際、仲裁に入りこちらを助けてくれる生徒が随分いた。
「あいつはあんなこと入ってるけど、本当はこう思ってて、だだ上手く言い出せないだけだから、先生の方で引き際をこんな風に作ってあげたら収まる。」
みたいな助言をくれる生徒は、今では殆ど考えられない。
また、クラス運営の相談役になってくれる生徒が結構いて、こちらが理解に苦しむ生徒について
「表向きあんな奴だけれども、実は家ではこういう苦労をしていて随分真面目にやってる。あれで先生のことわりに信頼してるから、しばらく放っておいた方がいい。」
といった助言をくれたものだ。もちろんこちらは所詮「先公」なのだから、生徒間で共有しこちらに明らかにしてはならないことは言わない。(少なくとも卒業式済むまでは。卒業後に聞く話はだから更に面白い。)細かい配慮を働かせながらこちらと接していた。こういう生徒が今なつかしい。
当時の生徒は、互いを理解する力が今と比べて格段に優れていたように思うし、他人を理解しようとする志向も今よりずっと強かった。クラスの他の構成員をどう理解するかという話題でクラスの生徒一人一人と長く話し込むことができた。教員に成り立ての頃、生徒とのこのような接触は、生徒を理解する力を付けるにあたり随分助けになった。生徒が育ててくれたと言ってもよいだろう。
こういう会話が現在の生徒となかなか成立しない。逆に、
「そんなことをしたら、彼がどう感じると思うか。」
という様な話=説教に生徒が何を言われたのかわからずぽかんとしている。心の奥底に届くだろうとこちらがかなり確信をもって決定打として放つ言葉が、透明人間にボールを投げたように、素通りしてしまう。空振り体験が増えた。
生徒が互いにあだ名を付けなくなった。昔は、本人の特徴を捕まえ本人もそう呼ばれて不愉快でないようなあだ名を上手く付ける生徒が必ずいた。教員にもあだ名がついた。今、生徒はお互いを名前で呼ぶことが多いが、あだ名を持った生徒はぐっと減った。教員もあだ名をもらわなくなった。これも、生徒の他者理解力と関係があるのではないかと思っている。
こちらの感情に鈍感になった。教員として、生徒の前に立つときはできるだけはっきり喜怒哀楽を表明するよう心がけているのだが、それに共振してこない。悪いことをした生徒には、思い切りこちらの怒りを表現する。それが上手くわかってもらえない。どうして良いのかわからずまごついている。かつては、殆どの生徒がこちらの怒りに共感してくれたし、なるだけ早くこちらの怒りを静めるための工夫をしたりり、逆に、「何とか笑わせてやろうか」知恵を働かせて振る舞う生徒もいた。だから今、体罰が成立しないのである。
横道にそれるが、体罰だけ取り上げてその是非を論じるのはおかしい。体罰を含めた指導全体に、適切な指導、不適切な指導、絶対してはならない指導があるだけ。体罰よりずっとひどく生徒を傷つける指導をいくらも見てきた。もうこちらが悪いことは百も承知しているし、濡れ雑巾で顔をなでるような説教を数時間食らうよりビンタで終わらせてくれ、という生徒だっていた。
人を理解する力はどんなものか改めて考えてみるとよくわからないが、文化とか思想の問題ではなくて人間が生命活動を維持するために必要な根源的な技能であるように思う。このような技能として、まず言語、その次が他者理解の能力だと思う。人間が言語を使用できるのは、まず生物として言語活動の資質を持っている上に、幼年期に言語使用について長時間のトレーニングをするからである。他人を理解することもこれと同じだろう。遺伝子情報は変わらないのだから、あとは幼年期のトレーニングが不足しているとしか考えられない。生まれてから思春期に至るまでに他者と接触するその総量が不足している。
家で夕食後の団欒が失われ、みんなテレビを見ている。更に、個室にこもってそれぞれ違う番組を見ていたりする。夕方、子供同士で遊ぶ変わりに、塾とお稽古事。これらについては、言語能力の意味からも改めて述べたい所だ。かつて学校は、相互に身につけた自己表現と他者理解の能力を出し合い磨く場であった。学校での生活時間は五十年前と同じだけあったとしても、そこで相互に出し合う基礎能力が落ちているから、かつてのような交流の深さ、相互の成長が得られない。
こんな風に感じている。
Author Archives: clahhfng
体育会系
「体育会系」という言葉がある。「4年神様、3年貴族、2年平民、1年奴隷」とは、昔からよく言われてきた事だ。私自身はその中に身を置いた事がないが、体育会と言わずとも寮などでもそれに似たような上下関係はあったようだ。40年前の話である。社会は、オイルショック、バブル、ベルリンの壁崩壊、・・。どんどん動いてきた。高度資本主義、消費社会、ポストモダン、グローバリズム、社会を分析する様々な言葉が登場した。共同体意識は失われ、大衆は消費主体としての個人に解体した等と言われる。
にもかかわらず、相変わらず「4年神様、3年貴族、2年平民、1年奴隷」は生き残っている。らしい。程度の差はあるだろうが、大学運動部の寮で1年生が4年生の「付き人」として奴隷のように奉仕する風習は未だ存在すると聞く。そんなことをしていたら、合理性を徹底的に貫く他国のスポーツトレーニングにかなうわけがないと思うのだが、これはの本題から逸れる。学年による上下関係は絶対であり、態度としての礼儀、言葉遣いとしての敬語は体育会で生き延びるための必要条件だ。同時にこれは、今の日本社会で円滑な生活を送るための技術でもある。「体育会系」は就職に有利。日本は変な国である。西欧社会学の概念を当てはめても分析できるわけがない。
この上下関係は、卒業後も保存され、社会に根を下ろす。「体育会系」は日本社会に親和性が強いから、社会の中心部にまで「体育会」出身者は多い。OB会は強い組織を持ち、裏のネットワークを作る。学校の教員も体育科の教員は全員、そして各教科に「体育会系」教員がいる。彼らはたいてい自分が属した種目の部活動を指導する。その指導に「体育会」の感覚を持ち込む。地域のスポーツ教室、少年団の指導者たちも「体育会系」。中学生の部活動加入率約70%、その70%が運動部に属するのだから約半数の中学生は運動部で活動し、多かれ少なかれ「体育会」の空気を吸っていることになる。
体育系部活動では、先輩、指導者への礼儀と言葉遣いが教えられ、それを守る事が強く求められる。実際、それが部活動の最大のメリットであると考える保護者も多い。その程度は運動の種類、学校、地域でまちまちだろう。また、生徒間の上下関係と、指導者対生徒の関係は別に見るべきかも知れない。誰か調査研究してほしい。しかし、都道府県大会、全国大会で実績を残すような部活動ではほぼ例外なくこの関係が強く成り立っていると言って間違いない。従来指導者に対しては無条件の服従が理想とされてきた。過酷なトレーニングを要求し、実績を残すのである。
大学の「体育会」頂点とする運動部の世界は、日本の縦社会を補強する大きな材料になっている。
「教員の指示に従う」、学校ルールを無条件に承認するする生徒が供給されるのだから、教員にとって、礼儀と言葉遣いを仕込まれた運動部員は好都合な存在である。直接その部を指導しなくても同じ学校に勤務すれば、「自分が頭の上がらないA先輩が指導を受けた先生なのだから、自分もまた従って当然」という無限ループができあがり、こちら側の何の努力なくとも生徒が指示に従うようになる。こんな楽な事はないのだ。そして強い部活動に属する生徒は、教室内でも他の生徒が一目置くから、教室全体が指導しやすくなる。
現代社会で、学校の中で生徒が教員の指示に従わなければならないのは、それが学校教育の仕組みであり、そうしないと円滑な運営ができないからだ。別項でも述べたように、サッカー試合の審判のようなものだ。学校で教員の指示に従う事は、生徒の自覚的な学校教育への参加行為の一部であるべきだ。「体育会」的発想がもたらす最大の問題点は、この社会組織への主体的な参加意識を抹殺してしまうとことだ。生徒は、「今ここが縦社会的振る舞いを求められているか」「ここで縦社会的振る舞いを逸脱するとどのような社会的制裁を受けるか」いわゆる場の空気に対する感覚を研ぎ澄ます。
運動部指導者の中に、本来的に生徒を育てる目を持ち、同時に競技とそのコーチングに豊富な知識と経験を持った優れた指導者はいくらでもいる。形としての上下関係裏に、深い信頼関係が成立している事は多い。この、型の実質を作る信頼関係が怪しくなっているのがもう一つの問題点だ。別項で述べたが、子供たちの対人関係に関するスキルは確実に落ちている。これは生徒間の関係のみならず、他者全般に及ぶ。他者を主体的に評価する力量が落ちている。敬語を使うときも、心から尊敬して敬語を使う、その場が求めるから形式的に従って敬語を使う、こういう事に、かつての生徒の方が自覚的だった。
新任の頃、生徒から他の教員の評価、噂話を聞くのは、結構楽しみの一つだった。特に、指導する部活動の生徒なとは普通の教員対生徒とは別の親密な関係が作れるから、合宿の折など面白い話をいくらでも聞けた。学校内にスパイを放っておくようなものだ。独特な視点から下される人物評価は勉強にもなった。生徒間で教員がどう評価されているか、お互いによく知っていた。日常の会話の中で、他者をどう評価するか豊富な話題が存在したのだろう。
教員にこちらが感心するような巧妙なあだ名がついた。あだ名は、的確な人物評価と表裏一体だ。教員をあだ名でしか知らない生徒もいたし、教員間でも生徒の付けたあだ名が流通した。最近、教員のあだ名がめっきり減った。
某高校で起きた、コーチの暴力と生徒の自殺もこういう文脈で起きたと思っている。教員が思っているような信頼関係が実は生徒との間に成立していなかった。これは最近よくある話なのだ。
「体育会」のもたらす縦社会がどんどん形骸化し、社会参画の主体性を奪い、競争社会での子供たちの孤立を促進する後押しとなっているように思える。
1年生が4年生の付き人になることが、そのチームが強くなる事に貢献するはずがない。自分の精神的肉体的条件の管理方法を下級生に教えるのが経験者の役目だ。誰でもわかるこういう不合理を、黙って承認しなさいと「体育会系」は教える。
自己評価
子供の自己評価が低いとマスコミではよく言われている。いろいろな調査が行われている様だが、たとえばインターネット上にこういうデータが公開されている。
「高校生の心と体の健康に関する調査」
日本青少年研究所 2011年2月発表 より
問30 あなたは自分自身をどう思っていますか。
4) 私は自分を肯定的に評価するほうだ
日本 米国 中国 韓国
1. 全くそうだ 6.2 41.2 38.0 18.9
2. まあそうだ 30.8 35.0 44.6 51.6
5) 私は自分に満足している
日本 米国 中国 韓国
1. 全くそうだ 3.9 41.6 21.9 14.9
2. まあそうだ 20.8 36.6 46.6 48.4
確かに、米国との差は極端だ。謙虚を美徳とする日本文化と、自己表現力を最大限評価する米国文化の差はあると思う。しかし、それでは済まないある種の真実をこのデータは語っている様に思う。
自己評価とは何だろうか。こういう体験がある。ある生徒が教員室へ進路相談に来ての発言だ。
「大学へ行きたくなりました。私は馬鹿です。理解が人より遅い。でも体力あります。人の倍勉強する自身あります。これからの勉強の方法を教えて下さい。」
素晴らしい生徒だ。この発言を聞いた瞬間この子が進路目標をかなえるだろう事を確信した。実際その通りになった。こういう子供を育てた保護者を尊敬する。自己評価の高さとはこういうものだ。残念ながらこういう生徒に巡りあう機会がどんどん減っている様に感じる。
この子は、自分の能力の限界を周囲にさらけ出す事を怖れない。努力の結果が失敗に終わる事を怖れない。だから自分を賭けることができる。挑戦する事ができる。なぜなら、自分の存在価値を学習能力とか進路などとは全く違う次元でしっかり確保しているからだ。他人と能力を比較しても、結果が失敗に終わっても、そんな事では傷つかない別の次元で自尊心を保持している。彼は、自分の存在そのものの価値を信じている。
この確信は、具体的な人間のふれあいの中で生まれる。A君はA君だから価値がある。そういう人間関係からしかこういう自尊心は育たない。その基本はやはり親子関係だろう。子供が可愛いのは、何かの能力に優れているからでも、見た目がよいからでもない。ただ自分の子供だからだ。それは誰とも交換できない絶対的なものだ。その関係が親族に、地域に広がり、人は自尊心を形成する。人間はこういう風に家族を作り、共同体を作り生き延びてきた。自己評価は、自分で与えるものでなく、社会から与えられるものだ。
子供の自己評価の低さは、このような緊密な人間関係が失われつつある事を示しているのではないか。まず親が子供に対し絶対的な愛情を示さなくなりつつある。いや示しづらい社会になってきた。保護者の所でも書いたが、子供がただ元気に生きていればよかった時代は失われた。子供は小さいときから序列化・数値化され、その物差しは、家庭にも持ち込まれる。小学校1年生が塾に入るに際し知能検査を受け、知能指数が本人に告知されると聞いて愕然としたのは随分前の事だ。親は自分を子供に投影し、子供を達成度で評価する。学業成績だったり、スポーツ大会の結果だったり、お稽古事のすすみ具合だったり。
「能力」の社会的な評価は自己評価の根本を形成できない。それは、何かができれば自信はつく。しかし、数値化された序列には必ず上がある。そして同じ数値の匿名の誰かと常に交換可能だ。
自己評価は伝染する。自己評価が低い人間に他者の存在を絶対的に肯定する力はない。自分を肯定してこそ他者を肯定できる。自己評価の低い人間がそのまま大人になって自己評価の低い子供を育てる。今、日本はこの負の螺旋を突き進んでいる。同じ理屈で、自己評価の高い生徒を育てるためには、自己評価の高い教師が必要なのだ。
昔の親の様に子供を育てよう。何かができたら、と言う条件付き子育てを止め、無条件に子供を大切にしよう。親は、まず自分の人生を、今の自分を肯定し自己評価を高めよう。
学校という仮の社会でも、それが劇場空間であったとしても、個人を絶対的に大切にする事を真剣に教えよう。劇場空間だからこそ、「ごっこ」の世界だからこそできる事がある。温室の中では、厳しい自然界では決してできないうつくしい花が咲く事がある。こういう観点から教育を根本的に組み立て直すとどんな学校ができるだろう。
実際には絶対的な他者の肯定、絶対的な自己肯定は簡単な事ではない。むしろ究極の理念であって、実現はできないものなのだろう。実現したとき、それは死を意味するのかもしれない。
宗教と愛と死は同じ点に収斂する。
アスペルガー症候群
アスペルガー症候群は高機能自閉症とも呼ばれいわゆる自閉症とは若干ずれた概念だが、ここでは自閉症・アスペルガーまとめて漠然とアスペルガー症候群として考えるところを書く。
自閉症、アスペルガー症候群等の言葉を仕事上の問題として意識したのは、今から15年ほど前のことだ。それ以前から言葉としての「自閉症」は知っていたしそれに関する本が数多く出ていていたが、自分の担当する生徒の中にそういう生徒がいることを知らされたのは初めてだった。
そもそもこの概念自体が新しく、日本で広く認知されるようになったのが90年代の後半か。また、その原因も特定されていない、少なくとも社会的に広く承認されているものはない。また、アスペルガー症候群はある種の「障害」と考えられ重度の場合生活するにあたっては誰かの補助を必要とするが、行政による制度的保障は遅れているのが現状だ。
確かにそのような傾向を持った子供は存在し、その指導のため教師がこの症候群の知識を持つことは非常に大切だ。生活指導の様々な局面で「通常の」生徒とは異なる配慮が是非とも必要な場合がある。ETV特集で放映された(2013年3月3日、優れたドキュメントだった)ようにいじめの標的にされやすいのも事実で、いじめの問題を考えるに際しても必須の知識だろう。
一方、その扱いは大変微妙で素人が本を数冊読んだ位である人物がアスペルガー症候群に属するかどうか識別できるものでは決してない。長く専門的に学習し訓練を積んだプロに委託しその判断を仰ぎ場合によっては共同で作業にあたる必要がある。いわゆる学校カウンセラーでもアスペルガーについて専門的トレーニングを積んだ人は現在稀で、私の場合でもカウンセラーと共同で地域の信頼できる専門家のいる公共施設(児童相談所等)と連携をとる事になった。
最近「アスペ」と言う言葉が安易に流通し、差別的言質として使われるようになりました。これは大変危険な兆候で、その意味からも本当に慎重に事を進めるべきだと思う。
医者が自分の専門範囲外で手に負えない患者に出会った場合、求められるのは適切な紹介状を書く知識と判断力だ。同様、教員が教科指導のプロであると同時にアスペルガー診断のプロであることは不可能なのだから、必要なのはプロに委託し共同作業をするノウハウを持つことだ。まず、身近に信頼できる専門家がいるかを知ること、それが学校単位で共有されていること。これはもっと全般の精神疾患の場合も同じだ。
アスペルガーを疑われる子供の診断の場合、保護者にその問題を理解してもらうことが第一の関門になる。例えば、目の不自由な子を持つ親の場合、生まれたときから親はその事実を受け入れその子と生涯を共にする覚悟をするが、アスペルガー症候群の診断を十代になって受ける場合、保護者は今まで「健常」だと思っていた子供が障害者であることを改めて受け入れる心構えをしなくてはならない。これは簡単なことではない。逆に教育に散々苦労し、やっと解決の糸口を見いだす思いで受け入れて下さる保護者もいる。いずれにせよ、アスペルガーを疑われる生徒についてその専門的な診断を受けるにはしっかりした知識と慎重な判断、保護者を含めた本人を取り巻く社会全体の了解が必要で、少なくとも一人の教師の判断では事を進められない。
重度の場合幼児期に保護者が気付きここまで保護者として処置をとってきた場合もある。私が最初にあたった事例はそうだった。しかし学校が適切な処置をとるため随分時間がかかっている。ここが今私たちが考えなければならない問題点だろう。
アスペルガーは症候群と呼ばれるある種の傾向で、脳の器質障害であろうと言われているが、あくまで傾向で、私はどうも人間のある種の資質・能力の度合いの問題であるように感じる。音楽を聴いても、初めて長大な交響曲を聴いてその構成と書き込まれたドラマを深く理解し感動する人から、何度か聴くうちにだんだん親しみを感じるようになる人、何回聴いても雑音にしか聞こえない人までその聴き方は千差万別だ。同じように、人間の感情を理解する仕方も人によってまちまち、その中で特徴的な傾向を取り上げたものの一つがこの症候群で、多次元に連続的に広がっているように思えてならない。どこからがアスペルガーでどこまでが「健常」か線を引くことはむつかしい。しかし一方で、この傾向が極端な場合、十分な理解と配慮が必要なのも事実です。生徒一人一人の個性を理解して指導する必要があると言ってしまえばそれだけなのかもしれないが。
我々教師集団の中にもこの症候群に属する者はいないか、私自身はどうか、これも考えて見る必要がある。カウンセラーがその疑いを持った教員はいたし、生徒指導が苦手でよく問題を起こす先生に素人目でもその傾向を感じることがある。この症候群が社会的に認知されたのがごく最近なのだから、社会的にも本人もその自覚を持たないながらこの症候群に属する教員は統計的に推測すれば全国に数多く存在するはず。魔女狩りや差別の危険を一方でしっかり踏まえつつも、考える必要はあると思う。
何故近年になってこの症候群が注目されるようになったか。これも大脳生理学などの研究が進行中、安易なことは言えないが、私見を少し。昔からちょっと違った子供は沢山いた。子供は大体閑で遊ぶ時間には子供集団を形成しかなりの年齢差の子供が集団をなして遊んでいた。かなり幼い子供から小学校高学年まで流動的な集団を形成しながら親が晩ご飯で呼びに来るまでいろんなことやっていた。その集団の中で、どの子も他者との接し方を訓練してきた。今ならアスペルガーと分類される子もこの遊び集団の中でそれなりに社会的振る舞い方を時間をかけて学習していたのではないか、また周囲の子もちょっと変わった子とのつきあい方を身につけてきたのではないか。子供集団の体験が薄れ、子どもたちの社会的能力の低下ががアスペルガーを問題として浮き上がらせることの一つの要因になったのではないか。
教師として仕事をしていく以上、アスペルガー症候群についてのある程度の知識と、どこに専門家がいるのか等地域社会の具体的情報を把握しておくことは必須事項である。
嫌中憎韓
近頃書店で隣国の悪口を書き立てた本がコーナーを作るようになった。多数の本が平積みで売られている。タイトルも宣伝用の「帯」も随分汚らしい事が書いてある。大体、他国の悪口を言えばきりがないのであって、米国について悪口をならべれば材料はもっとたくさんある。実際新書版にはアメリカ批判の本が随分出ているのだが、「反米コーナー」ができたり、「それでもこの国とつきあいますか」のような情緒的な帯は掛かったりしない。今のブームはそれから考えても異様だ。マスコミを通じてしかまだお目にかかっていないが「ヘイトスピーチ」の内容も同じく。極端な差別的表現が平然と大都市の街頭宣伝で行われる。この書物のブームを新聞が特集していて、『嫌中憎韓』と言うのだそうだ。妙な既視感にとらわれて考えてみると、小説「1Q84」の連想。これが私たちの住んでいた社会だったか。異世界に紛れ込んでしまった様な感覚。
高等学校では、(個人的な体験になるが)90年代後半から、読書量も多く多少なり政治思想に関心を寄せる理知的な生徒の中に、「右翼」的な発言をする生徒が現れ始めた様に思う。教員として人間的にも充分信頼できクラスでの人望もある生徒が、じっくり話してみると、かなり「右翼」的政治思想を抱えている。彼らが共通に語るのは、従来の「左翼的」言動は大変脆弱で、それに比べて「右翼」的言動に力を感じるのだそうだ。それまでは、およそものを考える生徒はどちらかと言えば「左翼」の側からの反体制的視点をとろうとしていた。もちろんそこには、「ベルリンの壁」に象徴される世界規模での社会主義国家の崩壊、日本での社会主義政党の凋落などが大きな社会背景としてあるのは間違いない。でもそれで説明を終えては前に進めない。
現在のような排外的言動が大衆的規模で現れると感じる様になったのは、インターネット掲示板でのいわゆる「ネットウヨ」の登場からのように思う。それまででも右翼政治団体はあって、街頭宣伝車が走り、日教組大会を妨害していたりした。しかし支持者拡大にはある限度があってある意味で安心して眺めていられた。その支持者の拡大が、2000年代違った様相を見せる。 「本音と建前」と言う言葉がある。この言葉に沿って考えれば、インターネットは「本音」でものを言う場を解放した。元来日本の文化の中に、「勇気をもって」「本音」を語る人間を礼賛する風潮がある。その傾向がどんどん助長されている。そして日本の若者が「本音」で語ると、差別、拝外。ある先輩が、「本音と建前」を「現実と理想」の文脈と取り違えていると指摘していた。維新の会代表は、そのために国際的に袋叩きにあった。「本音と建前」は国際的には全く通用しない日本の地方文化のようだ。理想をあくまで理想として語り続ける事が、外交と政治の国際基準だ。そして理想は「建前」ではない。
戦後の民主主義教育は、日本にどれだけの事を植え付ける事ができたのだろう。民主主義は「建前」にすぎず日本人の「本音」にはなり得ていないのだろうか。自由民主党という政党の存在に西欧人は首をかしげるという。自由主義、民主主義についてどれだけの人間がしっかり語れるだろうか。その違いを鮮明に表現できるだろうか。いや、我々は、自由主義、民主主義と言う言葉をどう使っているのだろうか。戦後民主主義は、占領国によって一方的に与えられた。長い苦難の末に一歩一歩闘いとるような過程を踏んでいない。そのため、「自由主義」、「民主主義」は深く考え込むことなくは無定義述語のように安易に使われてきた。相手を批判する道具としてこの言葉を使う事はあっても、その中身について腰を据えて考える事がどれだけあっただろうか。その付け払いが迫られている気がしてならない。
生徒に学級討論をさせる。たとえば文化祭の取り組みについて。議長はまずアイディアを求める。何件かの案が板書され一段落すると、多数決をとって、最大票を獲得した意見が採用されておしまい。後期中等教育完成の高校3年生でもこんな風であった。私が
「それは民主主義でないだろう」
コメントを入れると、生徒はきょとんとする。
「民主主義とは、他人の意見をよく聞き、議論を尽くす事だ。できれば全員一致になるまで討議を続ける事が望ましい。」
と言うと、
「そんな事はじめて聞いた」
と返ってくる。私たちは学校教育を通じて民主主義を教える事ができているのか。教員が民主主義を知っているのか。実践しているのか。学校運営は民主的で、教員会議は健全な討論の場になっているか。こう書くとブラックジョークの様だ。更に言うなら、この国の最高議決機関、国民の1/100000以下のメンバーで構成されたスパーエリート集団の議論の様子は民主的か。自分の主張を一方的に語り、他人の主張は野次と怒号で消してしまう。それを手本に子どもたちは育つ。
民主主義の基本理念である、あらゆる個の平等な尊重を、学校教育で教える場は殆どない。逆に、学校での生徒の行為は、数値化され序列化されている。進路先の偏差値、学校の成績、クラス内順位、あらゆるスポーツに順位がつき、文系クラブにもコンクールがある。その「成果」だけが重視され、目的と結果はすり替えられそのこと自体が忘れ去られている。他者は自分の相対的な位置を決定するための道具になる。社会に出れば最後には貨幣という絶対的数値基準が存在する。現行政府が、短期的な経済繁栄と排外的外交を政策をセットとして掲げるのは偶然でない。お金を儲けて、他人を見下して暮らす。それが「本音」なのだ。序列化すれば、上を見ても下を見てもきりがないから、序列化の中で自己を定めようとすれば、必ず「自分より下」を同定する作業が始まる。学校は、毎日丹念に差別と排外主義を教え込んできた。いじめを助長してきた。
私たちは、理想を語る事のたいせつさを忘れてはならない。いくら現実離れしていてもそれは決して「建前」ではないのだ。民主主義をどう教育するか、その前に教える側がどう理解し実践するかしっかり考えたい。
と、「理想論」を語ってみたくなった。
ブラックボックス
かつて、真空管ラジオの背面には必ず配線図が貼ってあった。我が家に初めて来たテレビの背面にも配線図が貼ってあった。多少電気の知識があれば全体を理解できた。各部品の構造も単純で高校程度の理科の知識があればその動作原理をすべて理解できる。ラジオ、アナログテレビの信号形式は広く公開されていたし、FMステレオの本放送が始まると、ステレオ放送の信号形式の解説と復調回路の作り方がラジオ制作雑誌に特集された。多少電気の知識があれば「なるほど」と納得できる程度のものだった。信号形式が単純だから受信機の構造も単純、理解も可能だし、自作や修理もできた。今でも中波ラジオは、部品4個でゲルマニウムラジオが組める。20年前ぐらいだろうか、実家の古いカラーテレビの色がおかしいので緑信号の系列を追跡し、電解コンデンサーを1個取り替えて直した事がある。
地上波デジタルテレビの信号形式を国民の何%が知っているだろう。秘密にされているわけではない。インターネット上でいくらでも詳しく知る事ができるのだが、その内容が複雑で専門知識をかなり蓄えないと「なるほど」と何得できないだろう。受信機はコンピュータの一種でありその内部を理解するのは簡単な事ではない。
自動車の仕組みも基本は極めて単純で、素人でも随分さわる事ができた。重たいので本格的な修理のためには、大型ジャッキとかクレーンとかが必要になるが。米国などでは自分のガレージで車を修理し、古い車を乗り回す人が今でも多くいる。しかし、「電子制御」が登場し、キャブレターが電子燃料噴射に変わり、変速機が電子制御自動変速になって車も理解不能になり、素人には修理不能になった。日本製のオフロード車は本当のオフロードでは役にたたないという話を聞いた事がある。電子回路なんて一切ない、昔のソ連製あたりの方が砂漠ではずっと信頼できるのだそうだ。テープとか針金で応急措置ができる。
レコードは音の振動がその形のまま溝に刻まれていた。画用紙に縫い針をセロテープで貼り付けたもので回転するレコードに触れれば音が聞こえた。銀色に光るプラスティックの円盤にはそのような親密性がない。原理は他の電子機器に比べれば単純な方だろうが、再生機はこれもほぼコンピュータ。高速に動作する超小型コンピューターが安価に入手できるようになってはじめて実用化された。
昔の黒電話、裏蓋のねじを外すと番号ダイヤルとベルが見え、マイクとスピーカーがつながっているだけでそれ以外の何もなかった。今の携帯電話は、30年前のスパーコンピュータを遥かに上回るコンピュータに制御されている。中身の全体を知っている人間は恐らく世界中に誰もいない。日本に数千万台ある携帯の中から1台を特定して回線を接続するためには複雑な手続きが必要だ。その概要も知らないから、脱走犯が携帯電話を使って警察に捕まる。
私が初めて仕事用に用いたPC、なつかしのMZ-80Bには全回路図とIPLの機械語語ソース、BASICインタプリタのkせつめいが記載されたマニュアルが附属していた。ソフトを自作しない限り動かなかった。図面を見て自作応用機器を接続して使っていた人が結構いたからこそ全回路図が掲載されていたのだろう。時代と共にPCの性能が向上し、それに反比例してマニュアルは薄くなる。
書き出せばきりがない。集積回路の技術、小型コンピュータ製造技術がもたらした劇的な環境の変化は、思い返せば、ほんの30年ほどのことなのだ。1970年代まで、私たちが生活に使う道具は殆ど全て内容が理解可能で、たいていの道具は素人でも修理も可能だった。少なくとも一人の人間がその全容を把握する事が可能だった。今、身の回りにいくらでもある、コンピュータ(PC、携帯、テレビ、CD、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、・・・)はその構造の全体を一人の人間が全て理解する事はできなくなっている。コンピュータ心臓部であるLSIは数千万から数億の素子が配線されて成り立っている。それを動かすソフトウエアはたとえばウインドウズ7で5千万行以上のソースコードで成り立っているという。この全体を誰が把握できようか。同時にその製造のためには、巨大な資本と情報の蓄積が必要であり、「パーソナル」なコンピュータが世界的な寡占状態でしか提供されない状態が生まれている。我々の周囲をブラックボックスが覆う。意図的に隠されているわけではない。(そういう部分もあるだろうが。)規模が大きすぎ、内容が限度を超えて煩雑すぎるのだ。そのこと自体熟考を要する事なのだが、もう一つ気になるのは、このような環境で育った子供たちだ。
我々は、この30年を大人の目で見ながら通過する事ができた。新しい機械をそれなりに納得しながら使おうとしてきた。今の子供たちには、はじめから電子機器がある。予め理解を拒絶した道具に囲まれて育つ。大体素人の修理を想定していないから、簡単に内部を見る事はできないし、仮に見てもLSIが何個かペタッとついているだけだ。ゲーム機にしてもテレビにしても携帯にしても、その動作に何の疑問も持たない子供たちが大半だろう。二進数を教えたついでにCDの信号について話したら、日直日誌に「考えたら不思議一杯」とあった。後で記載した生徒と話してみると、今まで疑問にも持たなかったという。疑問に思っても無駄だから、与えられたものを素直に受け入れ活用しなさい。今の子供は、幼少時から自然にそういう訓練を受けて育つ。この発想は身の回りの物理的道具に止まらなくなるだろう。自然現象に疑問を持たなくなり、社会制度に疑問を持たなくなり・・・。
子供たちの批評精神を育てようとするとき、このブラックボックスをどう扱ったらいいだろうか。
授業プロとしての教員
授業にたつ教員は、舞台俳優もしくは落語家と似た仕事だ。誰でも教師として登場すれば師であると言うが、それは人間的な人生の師であって学校教育の授業それだけでは収まらない。20人から50人の集団を相手にして行う「授業」は細かな技術の集大成であり俳優と同じように長い修行が必要でありいつまでたっても「終わり」や完成はない。普段はあまり意識しないのだが教育実習生がやる授業、新任の教員がやる授業を参観させてもらうと、指摘したくなるポイントは本当につぎつぎ出てきてきりがない。ドアを開けて教室にはいるところからチャイムが鳴って授業が終わり教室を出るまで、さっとメモをとっても何十項目もあげることができる。その中にはちょっと配慮しなければならないことから、長い時間かけて自然に身に付いていくこと、どの教科でも同様なことと、教える教科で特有のこと、更に教科の中での特定の素材を教えるために必要なこといろいろ。これらのことを身につけながら、プロとしての教員、プロとしての授業を目指す。熱意が一番という人もあるが、人格や熱意だけで技術のない医者が話にならないように、熱意だけでは教師はやれない。
どこかで、落語家が真打ちになるのに必要な修行時間は一万時間というのを聞いたことがある。これはプロになるために必要な練習時間の目安として、およそあらゆる分野について当てはまることのようだ。プロスポーツ選手になるための練習時間、プロ演奏家になるための練習時間もおよそこれくらい、まあ対数的な感覚で千時間ではとても足りない、十万時間では一生かかるという意味でこれくらいなのだろう。およそ、1日3時間と見て10年。こんなものだと思う。私も、教師を始めて十年たった頃から自分なりの授業が出来るような気がしてきた。教員としての修行も授業一万時間が一つの節目になりそうだ。
雲
宮崎駿の描く雲が好きだ。雲は、花のように見つめるものではない。眺めるものだ。彼のアニメに登場する雲を見ると幼年期、自宅の縁側から売ることもなくぼんやりと眺めていた夏雲を思い出す。近所に大きな松の木が見えて、その向こうに入道雲が湧く。もしかすると、彼のアニメを見てから再構成された記憶かも知れないが。
雲はぼんやりと過ごす時間がないと眺められない。雲は神の芸術。雲は未来の予感、運命の告知である。雲を眺めながらいろいろなことをかんがえていた様な気がする。今思えば、それは、私にとって大変貴重な時間だった。
宮崎駿もそうだったはずだ。空へ、飛行へ憧れた。彼のアニメには必ずうつくしい雲と飛行シーンが登場する。『ラピュタ』は雲を描くために作られた作品である。
今の子どもたちは雲を眺めるだろうか。子供がぼんやりと過ごす時間を作り出すことを、保護者も教員も怖れている様だが、大きな間違いだ。ぼんやりする子は育つ。
教員は役者
教員となって十年経った頃、予備校講師の模擬授業参観が私の一つの転機になった。予備校の講師は授業のプロだ。授業が受験生に評価されまた教えた生徒の伸びと進路が予備校に評価されて、契約の更新がされ給与が決定するハードな世界を勝ち抜いてきた人たちだ。評価システムの是非、授業内容の是非はともかく、授業技術については学校教員より厳しくトレーニングを積んできたこと間違いない。さてその講師だが、会場に到着して控室に通したときは、神経質で無愛想な中年サラリーマン、ぶすっと黙りこくってこちらの挨拶にもちょっと答えるだけ。意外な人物でがっかりもし、心配した。ところが、生徒の待つ大教室に入るや一変。からっと明るい顔になったと思うや
「やあ君たち!こんにちは。僕を呼んでくれてありがとう!」
そこからノリノリの授業。内容も見事。最後に
「時間が来ちゃったからこれで終わるけど、続き聴きたかったら××予備校で僕の授業受けてくれ、さようなら!」
明るく元気に授業終わって控室に帰ってくると、ブスッ。元の暗い人物に戻り、当然のように謝礼受け取ってさっさと帰って行った。そこで私は授業する者の二重性、役者としての教員に改めて気付かされた。
教壇に立つのは、私ではない。私が演じるA先生だ。私は、教壇に立つA先生の性格を設計し脚本を作りそれを演じる。一人芝居。誰だって教員はそうしている。問題はこのことににどれだけ自覚的かだ。いわば素の自分、役者として教壇に立つ自分、その二重性を対象化しようとするもう一人の自分にうまく分裂していくことが大切のように思う。更に言えば、素の自分なんて無いわけで、家族と顔合わせているときの自分、一人になったときの自分全部違うキャラクターであるように、教壇に立ったときの自分はまた違ったキャラクターであることを自覚し、利用しどう演出するかなのだ。私自身、どちらかといえば人付き合いの苦手な孤立を好む人間なのだが、教室入ったら生徒に対して思いっきり友好的な明るい教員を演じきるよう心がける。生徒の反応見ながらその場で臨機応変に台本を書き、役者としての自分に指示して役を演じさせていく。数学の授業するA先生、HRでクラス集団を相手にするB先生、個人的に相談にのるC先生と似てるけど多少違った役柄を用意し半ば無意識に使い分けているように思う。この二重性を強く意識するようになってから、プロとして授業技術を磨くことが自身自分の中で上手く整理が付き、教員の仕事が随分楽になり、また楽しくなった。
数年前新聞で、ロックシンガー目指していたがこの道を断念し教員になったという人の記事を読んだことがある。彼は「教員になってみたら、1日に何と3ステージもライブが出来る。こんなすごいことはない。」と語る。この人はいい教員になるはず。私が長い時間かけて意識するようになったことを、ロックシンガーとしてステージに立っていたからこそ、パフォーマーとして教壇に立つことを感覚的につかめている。教員は役者であり、授業は祝祭だ。パーフォーマーとは単に役者であるだけでなく、生徒を単なる観客ではなく、祝祭の参加者として導き入れる能力を持つことだ。簡単に言えば「乗せる」。生徒と教員が一体となって作り上げるお祭りのようになったとき時間はあっという間に過ぎていく。終了の鐘が鳴って生徒が「え、もう終わり?」といってくれたときほど嬉しいものは無いのだが、一年に数えるほどしかできない。
大学で受けた授業の中にもそういう授業があった。単に教授が教壇で話をし、数式は黒板に示すだけのごく普通の授業だ。1日1話題90分、その講義が見事なのだ。講義の進行と共に熱が入ってくると教授も上着を脱ぎ声にも力が入る。学生や聴講の大学院生立ち見の同僚教員まで教室全体が興奮し熱くなっていくのがわかる。そして燃え尽きるようにその日の話題が完結して終わる。毎回そういう講義をする教授がいた。これがいかに難しいことか、実際に教壇に立って三十年たち、そのすごさを改めて実感する。
トイレの鏡
公衆トイレには鏡がついている。手を洗うついでに髪の乱れやネクタイのゆがみを直す。自分の顔を見つめ女性なら化粧を点検するだろう。鏡がなくてはできないことだ。ネクタイのゆがみに気付いて良かったとは思っても、誰も鏡に感謝はしない。鏡があったおかげだと気づきもしない。そんな教員になりたい。先輩に聞いた話だ。