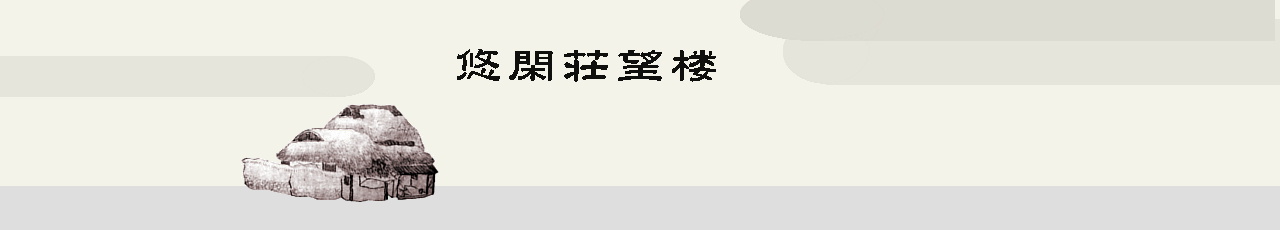一月中旬、生徒を殴る教師の動画がネットに投稿され、マスコミに大きく取り上げられた。「手を上げた教師ももちろん悪いが、生徒も悪い」当たりがこの動画の評価で、後は『炎上』に話題が移っていった。殴った教員、暴言を吐いた生徒、これを撮影しネットにあげた生徒。これらに対する評価はされている。しかし、この学校の教員集団についての言及があまり見られない。
私は、こんな学校で働きたくない。生徒とトラブルを起こしたとき誰も助けに来てくれない。
動画を見ると後方に生徒ではない人物が写っている。この人物は、生徒と教師を眺めて立ち去ってしまう。隣の教室から生徒が出てきて止めに入り終わっている。廊下にあれだけ罵り声が響いていて、他の教室の教員が出て来ない。教員が集まらない。「健全」な学校ではあり得ないことだ。同僚が孤立し生徒と揉めていたら、しかも、あのように生徒が興奮していたら、まず立ち会う。状況によっては更に同僚を集める。教員の頭の中にあるべき「危機管理マニュアル」の基本が、この学校の教員集団には欠落している。私自身、教員室から飛び出し全力で走った経験が何度もある。当たり前のことだ。
このような生徒は、他の生徒が見ている前では体面上引くわけに行かない。生徒の側には、体面を傷つけずに矛を収める口実が必要になる。『大勢の教師に囲まれた』は、その最初になり得る。そして、生徒を他の生徒の目線から外す。他の生徒がら隔離する。教員室なり別室へ連れて行くわけだが、これも教員一人では難しい。複数の教員で生徒を連れて行き、他の教員は野次馬生徒をそれぞれの教室に戻し、指示を与える。
高校では、教師の指示に従わず生徒の側から教師に向かって暴力的対応をした場合に、厳しい処罰が科せられることになる。あの動画のように教師が一人孤立してしまった場合、生徒を厳罰から守るため敢えて教師の側が先に手を出す、選択肢はあり得る。また、「殴られたので、先生の言うことに従った」となれば生徒の側で言い訳になる。体面を保って平静に戻ることができる。生徒を暴力的に従わせるのではない。生徒に矛を収める口実を提供するため、自分の処罰を覚悟して、生徒に手を出す。でも、これは最終手段。誰もこのような事はしたくない。そのために、教員の協力が要る。
学校は、大規模な生徒集団をその十分の一以下の教員で管理しなければならない。生徒が学校を潰すのは簡単なことで、何割かの生徒が示し合わせて授業のボイコットを続ければいい。また、どんなに「指導力」のある教員でも、興奮した数十人の生徒に囲まれたら何もできない。学校というのはそういうところだ。だから、教員が強い結束力を保つ事は、学校が機能するための第一条件。学校は教員の集団指導によって成り立つ。教員会議で激論を闘わせる相手であったとしても、生徒の前では同志。間違った指導をしているなと思っても、生徒の前では教員擁護。個人的には一分一緒にいるのも嫌な教員でも生徒の前では仲間。『Staff』として緊密な連係プレーを取り、統一された指導方針で生徒に接する。「校内暴力」と言われた時代、学校を正常に保つため、教員誰もが承知していたことが、忘れられてはいないか。
教員の個別管理が元凶。自分の担任するクラスさえ良ければいい。自分の授業さえ良ければ良い。それだけではない。余計なことはしない方がいい。自分が持つ方法論は同僚に教えない方がいい。更に、他の教員は失敗した方がいい。このような傾向は教員評価の論理的帰結として少しずつ学校を覆っていくだろう。
そして、廊下で孤立する教員の姿がインターネットに投稿される。
教員は大工もしくは落語家と同じ職人芸。一人前になるのに十五年はかかる。その間、先輩教員について技と知識を学ぶ。先輩は後輩を教える。仕事は教員相互で評価する。生徒は集団で指導する。トラブルには集団で対処する。百年を超す学校制度の歴史が示すノウハウである。それを文部科学省が、新自由主義が壊している。